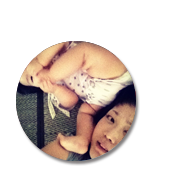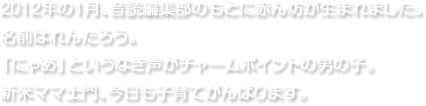まだ何もそこなわれてない生命が2017.12.31

この「子育て」についてのブログをずっと更新していなかったのは、今年一年が忙しすぎたのもあるけれど、やっぱり自分のなかの母親としての要素が少なくなっていたからかもしれない。
春、ふたりめの育休中にパートナーとふたりで出版社を立ち上げ、法人化した。夏に、もともと勤めている会社に復職した。そこからダブルワーク。フリーランスでライティングの仕事もしていたので正確にはトリプルワークだった。秋には一冊目の本『100年後あなたもわたしもいない日に』を、自分の出版社から著者のひとりとして出版した。韓国、台湾に出張に行った。本をたくさん売った。自分で注文を受け、自分で発送した。いろんな文章を、求められるものも、求められないものも、たくさん書いた。
暇があればリビングでパソコンに向かい、コーヒーを飲みながらキーボードを打ち続ける母親の横で、「遊ぼう」と廉太郎は何度も言い、朔太郎は抱っこをしてくれと泣いた。
廉太郎に「今は無理」と言いながら、朔太郎を膝に抱えてまたキーボードを叩き始める。朔太郎は一緒になってキーボードを叩こうとし、画面に「っっっっっっっk」とかいう文字がよく並んだ。やめなさい、と、まだ赤ちゃんの朔太郎の手を止める。それでもなお手を伸ばそうとするので、観念して朔太郎をこちらに向かせ、いないいないばあなどをやってみせる。そこでふとお兄ちゃんの廉太郎の視線を感じ、
「廉太郎、一回だけ遊ぼう」
と言って、めいろをしたり、どうぶつしょうぎをしたり、しりとりをしたりした。
本を出したあと、大学の友達と久しぶりに会った。
彼女にはこんなことを言われた。
「蘭はすごいね。どうやって時間をつくってるんだろうって、むかしから不思議でたまらないよ」
わたしはお酒を飲んで笑いながら、
「子供との時間を削っているんだよ」
と思った。すごいことでもなんでもないから、恥ずかしくて言えなかった。
保育園からの帰り道、
「きょうはしごとどうだった?」
と廉太郎に毎回聞かれる。
わたしが嬉しそうな顔をしていると「きょうはしごとうまくいった?」になるし、疲れた顔をしていると「きょうはしごとおこられた?」になるし、本当に彼はわたしをよく見ている。
「ぼくしってる。ママのしごとはことばをかくことやろ」
と言われたことがある。
「そうだよ」と言うと、「どうしてそれをしごとにしたの」と聞かれた。
「なんでやろ。わからんな」
「かくのがすきだから?」
「うん、そうだね。書くのが好きだからかな」
「むかしから?」
「そう、むかしから。廉太郎はどんな仕事したいの?」
そう聞くと廉太郎は、
「ぼくはママといっしょにしごとがしたい」
と答えた。
「ぼくはママとおないどしにうまれたかった。そうしたら、ママといっしょにしごとができるでしょ?」
旧姓の「土門」を再び使い始めたのは、今年の春からである。
これまでは結婚後の苗字で仕事をしていたけれど、育休から復帰するのを機に「土門蘭」として仕事をすることにした。
正直に言うと、結婚後すぐは、苗字が変わることくらい、どうってことないと思っていた。でもそんなことはなかった。わたしにとって苗字というのは、何事もなく置き換えられるものではなかったのだ。それはやっぱり大事なもので、それを変えることはやっぱりわたしの内の意識に変化を生じさせることだった。そしてわたしが文章を書くためには、その変化が生じる前の、とてもシンプルな状態に戻ることが必要だった。
「どもんらんってなあに?」
「土門蘭は、ママの名前。結婚する前のママの名前」
「ふーん。ママはどもんっていうのか」
廉太郎は母の日、スーパーマーケットで配られた似顔絵の紙の上に、リボンとハートをいっぱいつけた、わたしの顔を描いてくれた。
「なまえ」というところに、彼は最初「どもんらん」と書いた。
「そこは、廉太郎の名前を書くんだよ」
びっくりしながらも、わたしはそう言った。
「そうか」
と恥ずかしそうに笑いながら、廉太郎は消しゴムでその文字を消す。
「も、が逆だね」
わたしも笑いながら、消えていく文字を見ていた。
「お母さん、最近ちゃんと寝てますか?」
朝、朔太郎を預けているとき、保育園の先生にそう言われた。よほど疲れた顔をしていたんだと思う。
「最近夜泣きがひどくて」
と答えたら、帰りに先生に呼び止められた。
「お母さん、自分を責めてはだめですよ」
えっ? と言うと、彼は笑ってこう言った。
「朔太郎くんは、保育園ではとても穏やかです。お母さんと離れたあとも、いい子にしています。それはお母さんがちゃんと帰ってくるって、信じて安心しているからです。夜泣きをするのは、お母さんといっしょにいることが嬉しくて、甘えているからなんですよ」
だから、自分を責めないでくださいね。
保育士さんはもう一度そう言った。
まだ何もそこなわれてない生命が鏡文字で書く母の旧姓
わたしはそんな短歌を詠んだ。
まだ、短歌の本を出すだなんて考えてもいなかったころだ。
朔太郎は、最近少しずつ歩くようになってきた。
数秒のあいだひとりで立って、目が合うと嬉しそうに笑って、体勢がもたなくなるとはいはいをしてわたしのもとへ寄ってくる。抱っこをすると重たい。顔を近づけると、歯の生えそろった口からよだれを垂らしながら笑う。髪の毛やめがねを掴んで、ひっぱろうとする。
廉太郎は、4月から小学生になる。
ひとりでお風呂にも入れるし、洗濯物をたたむこともできるようになった。だけどこのあいだ初めて留守番をしたら、急にさみしくなって家を飛び出してしまって、わたしと入れ違いになって大騒ぎになった。付き添ってくれた見知らぬおばさんが「ママがだいすき、ママに会いたい」ってずっと泣いてましたよ、と教えてくれた。わたしが苦笑すると、廉太郎も泣き顔で恥ずかしそうに笑った。
まだ何もそこなわれてない生命たちに、わたしは日々、そこなった部分を癒されている気がする。
自分を責めているのは自分だけで、彼らは決してわたしを責めずに、いつだってやさしい。
どうかせめて、わたしだけは彼らをそこなわぬよう、と思っていても、それも叶わない自分が情けなくなるときがたくさんあって、
この本に廉太郎と朔太郎のことも書いたよ、と、許してほしくなって言う。
どこどこ?
と嬉しそうにのぞきこむ廉太郎と、ページをめくろうとする朔太郎が、やっぱりとてもかわいくて、完璧であることは叶わなくても、できるだけ善くありたい、と願う日々だ。