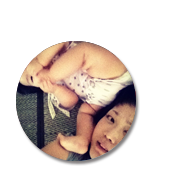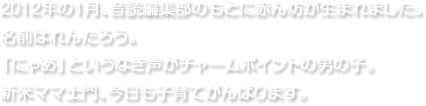母とわたしと、お母さんたち2018.7.10

昨年の秋から冬にかけ、次男の朔太郎の夜泣きがひどかった時期がある。ちょうどわたしが仕事の忙しい時期で、それが朔太郎にも伝わっていたのかもしれない。
朔太郎はそのころ、ほとんど毎晩のように泣いていた。
ぐずりだし、徐々に泣き声が大きくなって、それから2時間ほど止まらない。
いつもなら夫と交代しながら見るのだが、ある夜はわたしひとりで子守をしていた。その前の日も、ほとんど眠れていなかった。甲高い声に耳鳴りがした。赤い顔をしてふんぞり返る朔太郎に何度も蹴られた。
寝不足が続いていた。
体力的にも精神的にも、かなりきつくて、
(頭が、すごく痛いな)
そう思ったときには、わたしは朔太郎の口を抑えていた。
やめなきゃ、と思っている自分と、もっと力を込めようとする自分がいた。
わたしは、自分の手を自分で引きはがし、逃げるみたいに寝室から出ていった。
閉めたドアの向こうから、火がついたように泣き叫ぶ朔太郎の声が聞こえる。
両耳を塞いで一階のソファにうずくまった。耳の奥でずっと泣き声が響いていて、多分あのままだったらわたしは朔太郎を殴っていただろうなと思った。あんなにかわいい子なのに。いきなり口を抑えられて、苦しくて、びっくりして、こわかっただろう。すごく自分がいやだった。冷静にならなきゃ、冷静にならなきゃ、と自分に何度も言い聞かせた。
虐待のニュースを見るたびに、「なんてひどい事件なのだろう」と思うと同時に、もしかしたらいつか自分がこのニュースで報道される側になるかもしれないということを、考える。わたしは、テレビに映る自分の名前と年齢を想像する。
そのイメージは、子供を育てて時間が経つにつれ鮮明になり、ひとごとだとはもう思えない。これまで自分が取り返しのつかないことをしないでいられたのは、たまたまラッキーなだけだったのだ、と思うようになった。
簡単に限界は来る。
そのとき、閉ざされた空間で冷静でいられるほど、自分は強くなんかない。
そのことをわたしは、子育てのなかで何度も痛感して、そのたびに、取り返しのつかないことをしないですむように、なんとか逃げてきた。
わたし自身も、夜泣きの激しい子供だったらしい。
夜中じゅうまったく泣き止まないので、仕事で朝の早い父が怒り出し、母がわたしを抱っこして、深夜に近所を歩き回ったのだと言っていた。
「あのとき、公園でブランコに乗りながら、泣きやまんあんたを殺してうちも死んでやろうかと思っとったよ」
母は笑いながら言っていた。幼い頃はなんてことを言うんだろうと思っていたけれど、今はただ、そうなんだろうな、と思う。
朔太郎の一件があった次の日に、母が電話をくれた。
「何があったんね?」
よほどわたしは落ち込んでいたらしい。声を聞いてすぐに、母が異変に気付いた。
わたしは、「夜泣きがひどい。寝てない。つらい」と、電話口で箇条書きみたいに話した。
涙が出そうになって、ぐっとこらえると、声が震えた。
すると母は「一回切る」と言って、本当に一回切ってしまった。
そしてすぐに折り返してきて、
「今、あんたの口座に一万円を振りこんだけえ」
と言った。
「このお金で、なんかおいしいもんでも食べたり、好きな服でも買いんさい。ね? そしたらまた、がんばれるじゃろ?」
それを聞いて、わたしはびっくりした。そして、思わず笑ってしまった。
「ようわかるね、うちが喜ぶこと」
そうしたら母は言った。
「わかるわいね。あんたの母親じゃもん」
「無理しちゃだめよ」
「休みなさいよ」
優しい言葉はもちろんうれしい。だけど、実際にはそれができないから、あるいはそうできないと思い込んでしまっているから、ここまで参っていて、自分にはどうしようもない。
母はあのときそれをわかっていたから、すぐに電話を切って、声をかけるかわりにゆうちょ銀行へと走り、娘の口座に一万円を振りこんだ。
おいしいものを食べて、好きな服を買って、娘がどうにか、明日からも子育てができるように。
その一万円は、なんだかたくましさの象徴のように思えた。きれいごとではない、母としてのたくましさ。
「よかった、いま笑っとるね?」
安心したような母の声がする。
それを聞きながら、公園で泣いていた母にも、そういう人がいてくれたらよかったのにな、と思った。
朔太郎の夜泣きは、春を迎えると徐々に少なくなっていった。
母からもらった一万円は、なんとなく使わずにとってある。
このあいだ、子供達と一緒に動物園へ行った。
わたしがソフトクリームを持ち、それを食べている子供たちふたり。
そんな写真を送ると、母がLINEを返してくれた。
「蘭、ちゃんとお母さんしよってえらいね。お母さん、涙が出るよ」