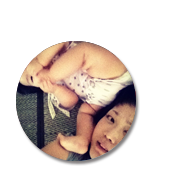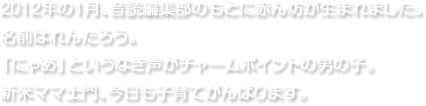わたしの6歳の子供たち2018.8.10

40度近い、酷暑のせいなんだろうか。
夕暮れの空がすごくきれいで、燃えるような赤色だったり、みとれるような紫色だったりする日が続いたことがあった。
窓の外を見ていた廉太郎が
「ママ、空がすごい」
と言う。
「ほんとだ、すごい色」
そう返すと、廉太郎は不安そうな顔で言った。
「ねえ、ママがこどもだったときも、夏はこんな空だった?」
あまりに赤いのでこわがっているらしい。わたしはよく思い出しもしないまま、
「こんな空だった」
と即答してやった。
「じゃあ、だいじょうぶ?」
「だいじょうぶ」
「そうか。よかった」
廉太郎が言い、今度は安心した顔でじっくりと空を眺める。
朔太郎はその横で、締め切った窓をぱしぱし小さなてのひらで叩いている。
廉太郎のその不安は、自分にも身に覚えがあるなと思う。
幼いころはいろんなことがこわかった。
地球温暖化も、自然破壊も、どこかの国の戦争も、親友の転校も、親の死も、幽霊も、すべてが同じくらいの質量でこわかった。
「だいじょうぶ?」
って聞いて、
「だいじょうぶ」
っておとなに答えてほしかったな、あの頃。と思う。
だから、自分の息子にそう答えることができて、わたしは満足した。
廉太郎が夏休みに入った。
とは言えわたしは仕事があるので、毎日廉太郎は学童に通い、朔太郎は保育園に通っている。
学童にはお弁当がいるので、毎朝作って持たせているのだが、あるとき時間がなくてコンビニで買ったサンドイッチとおにぎりを持たせたことがあった。白いビニル袋を提げて児童館へと入っていく廉太郎の後ろ姿を見ながら、「明日はお弁当を必ず作ろう」と思う。
帰ってきた廉太郎は、「みんなうらやましがってた。コンビニいいなーって。あしたもコンビニがいいな」と言っていたが、わたしはお弁当を作った。意地みたいなものだ。
毎日ちゃんとお弁当をつくるお母さんになりたい。
子供のころそう思っていたのを思い出したのだ。
夏休みは、小さいときのことをよく思い出してしまう。
パジャマ姿の廉太郎と朔太郎と、朝ごはんを食べていたときのこと。
テーブルの上には、わたしのつくったおにぎり、卵焼き、お味噌汁が並び、
起き抜けで腫れぼったい目をしているわたしの子供たちが、それらを食べている。
外からラジオ体操の音楽が聴こえてきた。
その拍子に、ふと自分の口からこんな言葉が出た。
「ママ、廉太郎くらいの年のとき、ずっとひとりでごはん食べてたな」
そんなことを言うつもりはなかったので自分でびっくりした。
夏休みは、小さいときのことをよく思い出してしまう。
「えっ、なんで? じいじとばあばは?」
廉太郎が目を丸くして聞いてくる。
「じいじは仕事でいないし、ばあばは夜働いてるから朝寝てた」
「じゃあごはんはだれがつくってたの?」
「自分でパンにジャム塗って食べてたよ」
そう言ったら、甘いものが好きな廉太郎は「いいなあ」と言うだろうなと思った。
でも廉太郎は言わなかった。そのかわりに、
「さみしかったね」
と言った。
「ママはこどものときから、ずっとがんばってたんやな」
それを聞いて、本当にびっくりした。
6歳のわたしが、6歳の廉太郎に、話しかけられているみたいだった。
泣きそうになってしまい、お茶を淹れに席を立つ。
うしろで子供たちがわたしのつくったごはんを食べている。
ごはんを毎日つくってほしい。
一緒にそれを食べてほしい。
絵本を読んでほしい。
宿題を見てほしい。
兄弟がほしい。
おじいちゃんおばあちゃんがほしい。
帰ったら家にいてほしい。
夜は一緒に眠ってほしい。
小さいころのわたしが望んでいたことを、気づけば今のわたしは、親の立場としてほとんど叶えているのだった。
そうか、と思う。
わたしはわたしなりにがんばっていたんだな。廉太郎の言うとおり、子供のときから。
今ここに6歳のわたしがいたらどう言うだろう?
空いた席に、6歳のわたしが座っているのを想像する。
髪が長くて、やせっぽちで、廉太郎と朔太郎に目がよく似ている女の子。
「ママ、空がすごい」
彼女もやっぱり、夕方にはそう言って不安がるんだろうか。
たぶんわたしは、廉太郎と朔太郎と一緒に、子供のころの自分も育てているんだと思う。