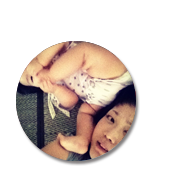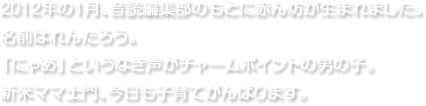誰の目線も届かない、自分のための世界を持つこと2018.9.1

このあいだ、ある映画を観た。
母親が癌になり、余命数ヶ月だと言われる。
だけど彼女は夫以外の誰にもそのことを言わず、娘にも何事もなかったように接するのだ。
そんなある日、娘が高校でいじめられていることがわかった。
朝、ベッドの中でぎゅっとうずくまり「学校に行きたくない」と言う。
わたしはそれを観ながら、自分なら何て言うかなあと考えていた。
「嫌なら行かなくていいよ」だろうか。
それとも「少しだけ休んでみようか」だろうか。
だけど、映画の中の母親はそのどちらでもなく、娘をベッドから引きずりだそうとしたのである。
「逃げちゃダメ、学校に行きなさい」と。
わたしはそのシーンを観て、とてもびっくりした。
いじめられて塞いでいる子をさらに追い詰めるように「逃げちゃダメ」と言って叱るなんて、厳しいなぁこの人はと。
だけど、映画が進むうちにこう思った。
もうすぐ自分が娘のそばからいなくなるのだと知っている彼女が遺したかったのは、「逃げる」ことじゃなく「立ち向かう」ことだったのかもしれない。なぜなら、娘に「立ち向かう」練習をさせられるのは、「帰る場所」として自分が存在している、そのあいだだけであることを、彼女は知っていたからではないかなって。
その映画を観ながら、わたしは自分の中学時代の、ある情景を思い出していた。
合唱の練習中、同じグループの女の子が、わたしに向かって自分の履いていた靴を投げつけたのだ。
わたしの紺のブレザーの胸元には、くっきりと彼女の足跡がついた。
なぜそうなったのかは、全然覚えていない。
ただわたしは何かやり返すことも、何か言うことも、それどころか足跡を払うこともできず、うつむいて涙を流した。クラスのみんなは、しんとしてわたしたちを見ていた。
「なんであのとき、やり返さなかったんだろうなあ」
今なら何すんだとかふざけんなとか言って胸ぐら掴んでやるのに。
だけどあのころは、本当に怖かったのだ。何も言えなかった。そのときだけじゃなくて、ずっとそうだった。わたしはいつもびくびくしていた。
そのことを、映画を観て思い出した。
このあいだ、取材先に向かう電車の中で、同行していたディレクターさんとカメラマンさんと
「いじめられたことってあります?」
という話になった。
わたしがその映画の話をしたからだったか、次に停まる駅がディレクターさんが昔通っていた高校の近くだったからか。
結論から言えば、みんな「いじめられたことがあった」。
「明確にいじめだったかと言ったらあやしいんですけどね。まわりから見たらそんなふうに見えなかったかもしれない。いじられるとか、パシリにされるとかの、延長線上だったので」
わたしがそう言うと、ふたりとも「そんな感じですよね」と言った。
カメラマンのYさんは、いつもつるんでいる仲間内で、ずっとそういう状態だったらしい。
「自尊心が毎日毎日踏みにじられるみたいな感じでしたね」
だけど、そのグループから出ていけなかったのだという。
わたしも、結局足跡をつけた女の子から離れられなかった。きっと、その子のことを友達だと思いたかったんだと思う。明確に上下関係のある相手を、友達とは言わないのに。
「卒業までずっとそんな感じだったんですか?」
と聞いたら、彼は首を振って、
「ちょっと転機みたいのがあって」
と言った。
「ある授業で、絵本を作ることになったんですよ。自分で物語も、絵も、文章も作る。それがなんか、すっごく楽しかったんですよね。で、夢中になって、めちゃくちゃがんばって作ったんですよ。そしたら自分でも『すごいのができた!』って思うくらい、いいのができあがって。先生とかにも『お前やるなあ』とか褒めてもらったりして。それを見たグループの奴らも『お前こんな才能あったんだな』って言って、一目置いてくれるようになったんですよね」
なんかそっから変わりましたね、と彼は言う。
その絵本は、雪だるま男が女の子を助けるという内容だったらしい。
「今思うとスノーマンなんですけどね」と笑う彼に、わたしは「いい話ですねえ」と言った。
「きっとYさんは、自分のための世界を見つけたんですね」
いじめが身近にあると、人からどう思われているのかをしきりに気にするようになる。
次のターゲットが自分にならないように、なめられないよう、バカにされないようにと気をつけるようになる。
するとどうなるかというと、自分の行動がすべて、「いじめられないため」に選択されたものになるのだ。
そうなると、すごく息苦しくなる。まるで自分の発言・行動・服装・趣味嗜好を、他人に支配されているような気持ちになる。
だけどYさんは、他人にどう思われるかなんて関係ない「自分のための世界」を持つことができた。そこに没頭することができた。
「『自分のための世界』を持つと、人って強くなれますよね」
わたしにとってはそれが「書くこと」だった。
何があっても、1日の最後に「書くこと」があればやっていけた。その時間だけは、自由だったから。
そのことを思い出して、なんだか嬉しい気持ちになったのだ。
ベッドの中から出てこない息子に、わたしは何て言うだろう。
電車に揺られながら、「逃げてもいいから、学校行かなくてもいいから、そのかわり『自分のための世界』を見つけなさい」って言うかなあと思った。
誰かに好かれたいからとか、バカにされたくないからとか、そんな他人の目線も届かないくらいずっとずっと奥にある、「自分のための世界」を。
先日、廉太郎が絵を描いていた。
夏休みの宿題で、動物園の動物を描こうというのがあったのだ。
真っ白い画用紙を前に、廉太郎がため息をついている。
描いては消し、描いては消しするので、「なんで消しちゃうの」と聞いたら、
「だってへたくそにかいたら、笑われんねん」
と言った。
「笑われるって、誰に」
「六年生の子に」
「笑わないよ」
「笑うよ、ぜったい。だから、うまくかかなあかんねん」
あんまり苦しそうに描くものだから、
「もし六年生の子が笑ったら、ママがその子をぶっとばしてあげるよ」
と言った。
「だから、描きたいように描いてごらん。どんなんでもいいよ。廉太郎が描いた絵なら、ママはなんでもおもしろいよ」
そうしたら彼は「ぶっとばすのはだめやとおもう……」と言いながらも少し笑って、それからもう一度、鉛筆を手にした。
「できた」
その声を聞き、わたしは絵を見にいく。
画用紙のなかでは、はじでうずくまるヒョウが、おりの中でさみしそうに、うつろな目でこちらを見ている。
「ああ、廉太郎の見たヒョウは、本当にこんな表情をしていたんだろうな」と思う絵だった。
「廉太郎!」
わたしは思わず声をあげた。
「とってもすてきな絵!」
廉太郎は恥ずかしそうに、にこにこ笑った。
靴を投げつけられても何も言えない弱虫だったわたしには、きっと廉太郎をベッドから引きずり出すことはできない。
わたしにできるのは、子供たちの「自分のための世界」、誰の目も気にしなくていい自由でいられるささやかな世界を、どうにか守っていく、それだけなのだと思う。