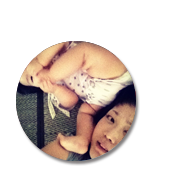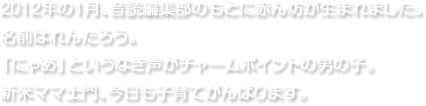舞台に立つこと2019.2.10

昨年の夏から、水泳を始めた。
廉太郎も昨年末から水泳を始めたけれど、今回は彼の話ではない。わたしの話である。
わたしは幼いころ習い事をしたことがない。
水泳も体育の授業でしかやったことがなくて、全然泳げなかった。
スイミングスクールに通っているクラスメイトたちは、信じられないくらいよく泳ぐので、彼らと自分を比べてしまうといたたまれなくなり、プールの授業が嫌で嫌でしかたなかった。よく嘘をついてずる休みもした。
あれは5年生のときだったと思う。
クラスに千恵ちゃんという女の子がいたのだけど、その子が50メートル泳げるようになって、わたしが「いいなあ」と漏らしたことがあった。
そうしたら千恵ちゃんがくるっとわたしを振り返り、
「卑屈じゃねえ」
ときっぱり言ったのだ。
すごくびっくりしたので、今でもよく覚えている。卑屈、という言葉が日常生活で使われるのを、わたしは多分、そのとき初めて聞いた。
千恵ちゃんは続けた。
「わたしは泳げるようになりとうて、練習をしたけん泳げるようになったんよ。蘭ちゃんは練習しとるん? 練習もせんと『いいなあ』ばっか言いよるんじゃない?」
バレエを習っている千恵ちゃんは、濡れた長い髪の毛を拭きながらそう言った。
もしかしたらバレエの世界では、こういうことなんて日常茶飯事なのかもしれない。
わたしは「千恵ちゃんの言う通りだな」と思った。千恵ちゃんの言う通り、わたしは卑屈だなと。
「わたしも、練習する」
悔しくて、それしか言えなかった。
千恵ちゃんは興味なさそうに「そうしたら」と言った。
それからわたしは市民プールに行って、仲良しの年上の女の子に教えてもらいながら、クロールを練習した。
土日の二日間練習した結果、それまでまったく泳げなかったのに、次の体育の授業では25メートル泳げるようになっていて、自分でもすごく驚いた。
うれしくてうれしくて、千恵ちゃんに報告をしに行ったら、
「すごいじゃん」
と言ってくれた。
「本当に練習するなんて思わんかったわ」と、笑いながら。
わたしはそれまで気の強い千恵ちゃんが苦手だったけれど、そのときすごく好きになった。
こういうふうにはっきり言ってくれる人って、なかなかいないよな、と。
千恵ちゃんが言ってくれたから、わたしは泳げるようになったのだ。
それから20年ほど経ち、大人になってから水泳を始めたのは、単純に体力をつけるためだった。
会社員生活を辞めて以来、自宅でデスクワークばかりなので、簡単に筋肉が落ちていく。
運動をしないので太るのかと思ったら、体重が5キロくらい減ってしまって焦った。
このままでは体力が衰える一方だと恐怖を覚え、何か始めようと思っていた矢先、編集者からプールをすすめられて、近所のジムに入会を決めたのだった。
水泳と言っても、教わることはしない。
週に一度好きな時間に泳ぎに行って、好きなだけ泳いで、帰るだけである。
だから、唯一泳げるクロールばかりしている。
そんな感じでも水泳を始めてから顕著に変わったことがあって、それは血圧が上がったことだった。
上の血圧が100を超えることなんてこれまでなかったのに、病院などではかる機会があるたび、きちんと100を超える数字を出せるようになった。
あと、ちょっと筋肉もついてきた気もする。
ジムで泳いでいると、よく隣のコースでキッズスイミングが始まることがある。
見学ルームの窓から、たくさんのお母さんたちが顔をのぞかせて、自身の子供たちが泳ぐのを見ている。
ときどき、お母さんたちと目が合うことがある。同い年くらいのお母さんたち。
そういうとき、なんだか不思議な気持ちになる。
なんだか反転したような。
自分が自分を覗いているような。
このあいだ、初めて平泳ぎができるようになった。
ずっとクロールしかできなかったのだけど、人が泳いでいるのを観察しているうちに、自分にもできるかもしれないと思うようになったのだ。
それでやってみたら、できた。
すごく遅いし、フォームもちぐはぐなのだが、25メートル泳げたのである。
壁にタッチして顔をあげた瞬間、「できた」と小さく声が出た。
普段使わない腕の外側の筋肉がぴくぴく震えて、なんだかおかしくなってちょっと笑った。
そのとき、窓から覗くひとりのお母さんと目が合った。
恥ずかしくなり目を伏せて、わたしは逃げるようにクロールで折り返した。
それでも、平泳ぎができた喜びは大きかった。
「できた、できた」と思いながら、プールから上がってシャワーを浴びる。
学童に廉太郎を迎えに行ったとき、開口一番に
「ママ、今日、平泳ぎできるようになったよ」
と言った。
すると廉太郎は「すげえ」と言ってくれた。
「廉太郎も、がんばって泳げるようになりな」
そう言うと、「そやなあ」と言った。
「ぼくも、がんばるわ」
卑屈にならなくて済む方法を、わたしは千恵ちゃんに教わったなと思う。
それは舞台に立ってしまう、ということだ。
舞台に立ってしまって、やってしまうこと。
誰かと比べる余裕もないくらいに、ただただ体を動かすこと。
あのとき見知らぬお母さんに覗き込まれながら
「ああ、自分はこのことを子供に教えたかったんだ」
と思った。
わたしはあのとき、隣で泳いでいる彼女の子供と同じ舞台に立っていた。
不恰好でも、平泳ぎは、泳いでみないと泳げない。
できなくていいから、たくさん泳ぐ。そうしていればいつか、できるようになる。
隣のコースで彼女の子供も、わたしと同じようなことを感じていたかもしれない。
子供時代というのは、舞台に立つことの繰り返しだな、と思う。
いっぱい転んで、いっぱい泣いて。格好悪いところをさらけだしながら、そうやって大きくなっていく。
この感じを、自分自身もずっと忘れたくないなと思った。
自分の子供が舞台に立つのを見ながら、自分自身も舞台に立っていたい。
なんでだろう、同じ景色を見ていたいのかな。
そこでしか交わせない言葉があると、思っているからかな。
あるいはわたしは、今もなお卑屈になりたくないのかもしれない、人生にたいして。
だからママも、水泳続けます。