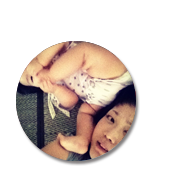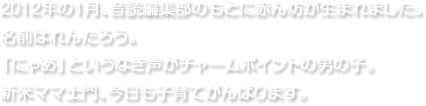家族の風景2019.3.1

毎週末、TSUTAYAでDVDを借りている。
子どもたちは子どもたちで、わたしはわたしで、それぞれ自分たちの観たい映画を選ぶ。
そしてそれを、お風呂から上がって眠るまでの短い間、一緒にソファに座って観る。
一気に観るのではなく、寝る時間になったらきりのいいところで(きりのいいところ、というのが映画にあるのかどうかはわからないが)中断して、二日とか三日に分けて観ている。こうするようになってから、ぐっと映画鑑賞に対するハードルが下がって、いろんな映画を観るようになった。今はだいたい、週に2本ほど観ている。
最近は、家族の生活を描いた映画を観ることが多かった。そのうちのふたつは、親が亡くなる映画だった。一つ目はお父さん、二つ目はお母さん。どちらも、ガンが原因で亡くなる。そして遺された家族が、きちんと弔う映画だった。
わたしの両親は健在だけど、祖父母は4人とも、わたしがものごころつく前に亡くなっている。
父方の祖母以外は、みなわたしが生まれる前に亡くなってしまっていて、写真も見たことがないし、実は名前も知らない。
なぜ写真がないのか、なぜ祖父母の名前も知らないのか。
両親がわたしに教えたり見せたりしなかったからなのだけど、ふたりがどうしてそうしたのかはわからない。
わたし自身もそういうもんだと思っていて、なんの疑問も持たずにやってきた。
わたしには母がいて、父がいて、ふたりだけが家族だった。
中学からはその両親も別居して、核家族がさらに細かく分かれることになったのだけど、これがうちの家族のかたちなんだからしかたないと思っていた。
わたしが結婚をし子どもを産むと、両親は自動的に祖父母になった。
目の前でふたりがそれぞれ孫を可愛がる様子を見ていると、自分が昔持っていなかったものが目の前にあるな、と思う。
子どもたちには、あなたたちのおじいちゃんおばあちゃんはこんな人で、こんなところで生まれ育って、こんな仕事をしていて、わたしをこんなふうに育てたんだよ、ということをときどき教える。長男は「ふううん」と言う。祖父が溶接工で原爆ドームの修復もした人なのだと知ると、「じいじ、すごいな」と喜んだりする。
それはまるで、分断されていたものをつなぎ直す作業のようだなと思う。
二つ目の映画について書こう。
ガンになったお母さんと、イラストレーターでありエッセイストの息子が、東京で一緒に住み始めるというお話だ。
お母さんは病気が悪くなり、途中で入院してしまう。
ある日その病室で息子が仕事をしていると、お母さんが
「まー君が仕事しよると、おかんは気分がようなるんよ」
と言った。
それに対して息子は「どういうからだの仕組みしてるんだよ」と笑うのだけど、そのひとことがわたしはすごく心に残った。
お母さんは病状がかなり悪くなってからも、息子の深夜ラジオを欠かさず聞いていた。
下ネタばかりで本当にしようのない内容なのだけど、嬉しそうにずっと聞いていた。
お母さんが亡くなった日、息子のもとに出版社から原稿の催促が来る。
息子は悄然としたまま、「あなたなら、母親が亡くなった横で原稿書けますか?」と言って電話を切るのだけど、そうしたら母の遺体の横に、若かりし頃の母が現れてこんなことを言うのだ。
「まー君、言うたでしょう。おかんは、まー君が仕事しよると、気分がようなるんよ」
それを聞いて息子は、母の遺体の横で仕事を始める。
「おかん、見といてよ。思い切り笑えるやつを書いてやるけんな」と言って。
それを見ながら、わたしだったらどうするかなあ、と考えていた。
そして多分、書こうとするだろうなあ、と。
父も母も文字を読む習慣がないので、わたしの書いたものを読むことはない。
母にいたっては、自分が生活費のために仕事ばかりしていて子育てに専念できなかった後悔があるらしく、「あまり仕事しなさんな」とよくわたしをたしなめるのだけど、これまでに出した出版物などはすべて手元に置いてくれている。
率直に言うと、寂しい幼少期だった。
祖父母や両親の揃った家が羨ましかったし、もっとお金があれば、と子どもながらに何度も思った。
だけどふたりは、わたしを精一杯育ててくれた。
そしてふたりのあいだに生まれたからこそ書くことと出会えたし、それを続けて仕事にすることができたと思っている。
わたしがこの仕事についたのは、ふたりの影響も多分にあるんだから、わたしが執筆を営み文章を世に送り出すことで、彼らもちがう形で社会で生き続けるような気がする。
だからきっと書くんじゃないかな。
わたしがちゃんと生きることは、彼らを生かすことでもあるから。
もうすぐ小2になる廉太郎は、最近漢字も読めるようになってきて、字幕の洋画も理解できるようになってきた。
「これはいい映画やな」と、一丁前に言ったりする。
ソファの上でぐすぐす泣きながら「ティッシュとって」と言うわたしに、廉太郎は素直にティッシュを持ってきてくれながら、
「ママはどの映画みても絶対泣くよなあ」
と言う。それでわたしは
「歳をとると人は涙もろくなるんよ」
と答える。
これは本当。
不安で寂しい子どもの気持ちも、もどかしく情けない親の気持ちも、今は両方わかる。
歳を重ねると、わかる気持ちが増えていく。
だから泣くんだよ、お母さんは。