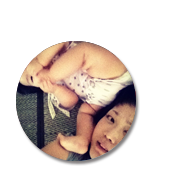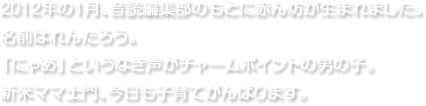「この光景をずっと夢見ていた気がする」2019.5.10

一人っ子で鍵っ子でとにかく暇だったからか、昔から本が好きだった。
その頃から、1日のうちでいちばん好きな時間は夜眠る前。
お風呂からあがったあとにベッドの中に本を持ち込んで、ふとんにくるまりながら読む。
どんな日も最後にはこの時間があると思えばがんばれるような気がしていて、今でもそれは続いている。
その習慣は廉太郎と朔太郎にも自然と受け継がれていて、わたしたちは毎晩、それぞれ自分の読みたい本を携えてベッドの所定の位置に潜り込む。
1日のうちでいちばん好きな時間を共有する相手ができたことが、わたしはとてもうれしい。
そしていつも、「この光景をわたしはずっと夢見ていた気がする」と思うのだ。
たとえば野球をやっていたお父さんが子供とキャッチボールをしたくなるような感じだと思うのだけど、わたしにとってはそれが「読書」なんだろう。
子供が本を読んでいるとなんだかいつも嬉しくなって、「あ、本読んでるね」「何読んでるの」と話しかけてしまう。
そのたびに廉太郎は表紙を見せてくれるし、朔太郎は「ぶっぶーちゃん(車の本)」「かみんらだー(仮面ライダーの本)」とか答えてくれる。
わたしは「ふーん」と、それだけ答えてもらうと満足して、自分の本を読む。彼らの本の中身を見ることはほとんどないし、それに口を出すこともない。薦めることもほとんどない。なんでもいいから、彼らが興味のあるものを片っ端から心ゆくまで読んだらいい、と思う。
わたしは多分「本」というもの自体がとても好きで、そして無条件に信じているのだろう。それに触れている子供たちを、誇らしく思う。
このあいだ、廉太郎が初めてわたしに本を薦めてくれた。
それは『シートンどうぶつ記4 銀ぎつね物語』という本で、学校の図書室から借りてきたのだという。
「ママ、シートン動物記は通ってないな」
と言うと、「通ってないってどういう意味?」と聞かれたので、「読んだことがないって意味」と答えた。
すると廉太郎は少し得意げな顔をして、
「おもしろいから、読んだほうがいい」
と言った。
「おもしろそう、読むよ」
と答えると、廉太郎は恥ずかしそうに、新しく借りてきたという本に目を落とした。
そのときふと、「あ、夢が叶った」と思った。
それはたとえば、野球をやっていたお父さんのミットに、ずばんと子供のボールが投げ込まれるような感覚かもしれない。
まさか「読書」という長年自分がいた領域で、自分の子供に古典を教えてもらうとは思わなかった。
時間がひっくりかえるような、いや、大きな輪の中に自分が立っていて、その輪にやっと気づいたような、うまく言えないけれどそういう気持ちになった。
わたしは、この光景をずっと夢見ていたな、と思った。それはなんだか、泣きそうになる気持ちだった。
廉太郎の薦めてくれた本は、とてもおもしろい本だった。
文字が大きかったので15分ほどで読めてしまったのだけど、一匹の賢い勇敢な銀ぎつねと、残酷さと優しさをあわせもつ人間、その人間に飼われる犬たちが、迫力ある筆致できちんと描かれていた。何が良いとか悪いとかではなく、ただそこには生きていこうとする動物たちの姿があって、わたしはそれに対する意見はなにも持てない、と思った。
だから、率直に感想だけ述べた。
「廉太郎、読んだよ。おもしろかった」
廉太郎は今夢中になっている『マジックツリーハウス』という冒険譚シリーズから顔を上げる。
「犬が狐を追っかけるシーン、捕まるんじゃないかってどきどきした。だけどあの犬もちょっとかわいそう。多分死んだよね」
すると廉太郎は「多分死んだな」とだけ言った。
「シートン動物記っておもしろいね。読んだことなかった」
そうもう一度言うと、廉太郎は恥ずかしげに、でもやっぱり得意そうな顔をして「うん」と言った。
「教えてくれてありがとう」
そのときまた、違うひとつの夢が叶うのを感じた。
でも、叶えたのは今のわたしではない。
叶えたのは、一人っ子で鍵っ子だった幼い頃のわたしであり、
叶ったのは、「お母さんやお父さんに、自分の読んでいる本を一緒に読んでもらいたかった」幼い頃のわたしの夢だった。
不思議だな、と思う。
ミットにずばんとボールを投げ込んできた相手もまた自分だったなんて、そういうことがあるんだろうか。
だけど、子供を育てていると、ときどき時間が線状から輪っか状になるのを感じるときがある。
まるで、幼い自分も一緒に育てているような。
朔太郎が「みてー、ぶっぶちゃん、かこいいねー」と言って本を見せてくる。
「本当だ、かっこいい」と返すと、真剣な顔でうなずいて、また本の世界に入っていく。
小さなわたしも、もしかしたらここで一緒に本を読んでいるのかもしれない。
そういうこともあるかもしれない。
そして、そうであったらいいな、と思う。