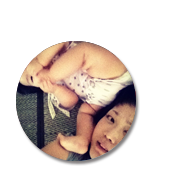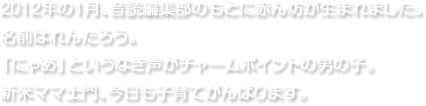8年間2020.1.10

今日で廉太郎が8歳になった。
母親になって8年。長いのだか短いのだか、よくわからない。
とにかく8年間ずっと、母親として夢中になって廉太郎の世話をしてきた。
おっぱいを飲ませ、おむつを替えて、お尻を拭いて、お風呂に入れて、着替えさせ、ご飯を用意し、絵本を読み聞かせ、靴の履き方や挨拶のしかたや物の名前を教え、たくさんの書類を書いて、保育園や学校や学童や習い事に通わせ、病院に何度も連れていって、誕生日を祝いクリスマスを祝い、夜は一緒に眠った。そんなふうにして、わたしは廉太郎を育ててきた。
特別なことは何ひとつしていないけれど、彼は大きくなっていった。友達ができて、本を読むようになり、自転車に乗れるようになり、ひとりでどこかへ出かけるようにもなった。
そんなとき突然、廉太郎が交通事故にあった。つい最近のことだ。お正月の三が日が終わって、明日から仕事始めだという日。昼から自転車で遊びに出かけていた廉太郎が、そろそろ帰ってくるかなと思っていた夕方5時。わたしの携帯電話に知らない人から電話がかかってきて、出ると、「息子さんが事故に遭いました」と言う。
彼女は廉太郎をはねたタクシーの乗客で、廉太郎からこの番号を聞き出したらしい。何かあったとき、たとえば迷子になったときのために、前々からわたしの電話番号を暗記させておいたのだけど、それがこんなふうに役立つなんて思ってもみなかった。
「えっ?」と驚くわたしに、彼女はすぐに「怪我は多分大したことはありません」と言う。
「だけどはねられたときにだいぶ跳んでしまったから、どこかぶつけていないか心配です。すぐに来れますか?」
彼女が言う場所は自宅のすぐ近くだった。わたしは携帯電話を握りしめ、コートだけ羽織って、慌てて家を出た。すぐに小さな人だかりが見え、走って近づくと、中央で廉太郎が突っ立ったまましくしくと泣いている。
「廉太郎」と言って駆け寄ると、廉太郎は泣いたままわたしの手を握った。
「けがは?」と聞くと、「わからない」と言う。
「ぶつかったときのこと、覚えてへんねん。でも、脚が痛い」
見ると、今朝わたしが縫い直したズボンの穴が再びやぶれ、真っ赤な擦り傷が見えていた。廉太郎が「直してくれたのに、やぶけてごめん」と言う。
「そんなの全然いいよ」
わたしはいったい何から確かめ何から手をつけたらいいのか、よくわからなくなってしまった。
ご年配のタクシーの運転手さんも軽くパニックになっていて、「119に繋がらない」と言う(あとから聞くと、Bluetoothに繋がって車内に音がすべていっていたらしい)。そこでちょうどパトカーが訪れたので手を上げて止め、警察と話をした。
「人身事故なので、救急車を呼んでください」
そう言われ、救急車を呼んだ。運転手さんとのやりとりは警察に任せ、連絡先だけ交換し、乗客の方に何度もお礼を言って、それから廉太郎とふたりで救急車に乗り込んで、近くの病院まで運んでもらった。
急患で運ばれた廉太郎は、傷を消毒してもらったあと、レントゲン室に向かった。
パンツ一丁になって台の上に寝そべって、心細そうにわたしのほうを見る。
「じっとしときや」
とわたしが言うと、「うん」と言った。その彼のからだを見ながら、小さなからだだなあ、と思った。もうだいぶ大きくなったと思っていたのに、まだこんなに小さい。
ふとそのとき、昔同じ場面を見たのを思い出した。あれは彼が2歳か3歳のときだ。あんまり廉太郎がよくこけるものだから、保育士さんに「脚のかたちに異常があるかもしれない」と言われて、矯正器具を作るためにレントゲンをとってもらったことがあったのだ。そのとき廉太郎はいい子して台の上に寝そべって、看護師さんに褒められていた。わたしはそんな小さな廉太郎が誇らしくって、かわいくてしかたがなかった。廉太郎のためにわたしができることはなんでもしてあげたいと思っていた。
そのときのことを不意に思い出して、少し泣きそうになった。
車にはねられたとき、もし何か違っていたら、何もかも違っていたかもしれない。
一所懸命育てていても、本当に、いつどうなるかなんてわからないんだなと思った。
廉太郎が生まれて間もないころ、その事実が本当に本当にこわかった。毎朝起きるたびに鼻に手をやって呼吸しているかどうか確かめて、ニュースで子供の事件を見るたびにおそろしくなって、この子がいなくなったらわたしはどうにかなってしまうと思っていた。
年月が過ぎるうちに少しずつその恐怖は薄れていったけれど、それがこの日、再びからだじゅうに濃くよみがえったような気持ちだった。
レントゲンに映る骨は、なんの傷もなく白く光っている。
「きれいだな」と思った。妊娠中、産院のエコーでも、同じようなことを思った。胎児の骨って、魚の骨みたいできれいだな。
その影を見ながら、わたしは昔のおそろしい気持ちを、ひしひしとまたからだ全体で感じ取っていた。
その日の夜は廉太郎はお風呂に入らなかったので、翌日の夜、お風呂からあがりたての廉太郎を呼んだ。
「ちょっとおいで。クリーム塗ってあげるから」
レントゲン室で見たとき、廉太郎の肌がかさかさに乾いていた。それを見て、ずいぶん長いこと彼のからだに触っていなかったなと思った。大きくなってひとりでお風呂に入れるようになってから、ほとんど彼に触っていない。
ほかほかとあったかくなった廉太郎は、タオルで拭いたと言っていたのにまだ全然濡れていた。わたしは「もう」と言いながら拭き直してやる。毎晩こんなだったんだろう。弟の朔太郎にかかりきりで、全然気づかなかった。
両手で顔にクリームを塗ってやっていると、廉太郎が目をつむったままちょっと笑った。
「なんか久しぶりやな」と言う。そうだね、久しぶりだね。わたしもそう答えた。
昔はかさかさのおしりにベビークリームをよく塗っていたよね。ぺんぺん叩いたら「きゃーっ」と笑ったことを、廉太郎は覚えているんだろうか。
クリームを塗り終え片付けようとしたら、ふざけた様子で背中に抱きついてきたので、後ろ手でぽんぽんとしてやった。
お誕生日おめでとう、廉太郎。
どうか何事もなく元気に育ってね。
もう、それだけで十分だ。