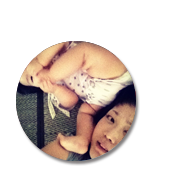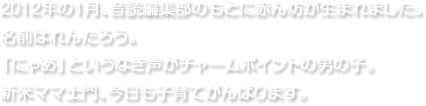初めて詩を書いた日2020.2.1

朝、廉太郎が突然「詩の書き方を教えてくれへん?」と言い出した。
その日の国語の授業で詩をつくるのだそうだ。
わたしは詩を書いたことはほとんどないけれど「書くこと」が仕事ではあるので、このように廉太郎から頼られたのが嬉しく「うん、いいよ」と快諾した。
聞けば廉太郎にはすでにモチーフがあるらしい。
「ダイヤモンドのことを書きたいねんけど」と言う。
「え、めっちゃいいじゃん!」とわたしは答える。
書きたいものがあるのはすばらしい。「何を書くか」が決まっているのなら、あとはそれを「どう書く」かを考えるだけだ。
「ダイヤモンドのどういうところを書きたいの?」
と尋ねると、廉太郎は不思議そうな顔をした。
「どういうところって?」
「きらきらしているところとか、すごくかたいところとか。廉太郎がおもしろいなって思うダイヤモンドの特徴ってなに?」
すると、「あ!」と何か思いついたのか、嬉しそうにこう言った。
「ダイヤモンドってな、最初はとげとげざらざらしてんねん。でも加工するときらきらになるんやって。それがおもしろいから、それを詩に書きたい」
その言葉を聞いてわたしはまた「え、めっちゃいいじゃん!」と答える。
ダイヤモンドの魅力をそこまで掘り下げられているとは思わなかった。
「でもそれをどういうふうに書いたらええかがわからへんねんなあ。それをそのまま書いても詩にならへんやろ?」
と廉太郎は言う。確かにそうかもしれない。わたしは少し考え、ひとつの例としてこんな提案をした。
「じゃあ、ダイヤモンドに似ているものが他に何かないか、考えてみたら?」
「え、どういう意味?」
廉太郎がまた不思議そうな顔をした。
「最初はとげとげざらざらしているけど、磨くときらきらになる。そういうのって、ダイヤ以外にも何かない?」
すると廉太郎はじっと考え込んで、「女の人……?」と言った。
「女の人はお化粧すると、きれいになるやろ? そしたら、モテるようになる。それってダイヤと似てるかも……」
「おおー、確かに!」
思わず笑ってしまったけれど、廉太郎はすぐにそのアイデアを却下した。
「なんか女の子たちに怒られそうやし、それを書くのはやめとくわ」
残念ながら彼の直感は多分正しい。わたしたちは他に何かないか考え始めた。
「朔太郎の髪の毛は?」
そう言うと、廉太郎は朔太郎のほうを向いた。
朝ごはんを頬張っている朔太郎の頭は、寝癖でぼさぼさだ。でもこの頭をブラシで梳くと、驚くほどつやつやになる。
なるほどな〜と廉太郎は腕を組んだ。ちょっと違うみたいだった。
「あ、心とかも似てない? ダイヤモンドに」
すると廉太郎がぱっと顔を上げ「心?」と聞き返してきた。
「心って放っておいたら怠けて良くないこと考えるじゃん。『面倒くさいから何もしたくない』とか『あれもこれも欲しい』とか『全部人のせいだ』とか」
「うん……そこまでは僕は思わへんけどな」
「でも、『ちゃんと生きよう』とか『優しい人になろう』とか思って心を磨くと、きれいな心になれるよね。まあそんなふうに、ダイヤと似ているものを探し出して、その中からおもしろいなと思うものを詩に書いてみるっていうのもひとつの手だと思うけど」
そう言うと廉太郎はパンと手を打って、「それや!」と言った。
心のことを書くのかな?と思ったら、そうではないのだと言う。
「僕、いまお母さんと詩の書き方について話してて、『詩を書けそう』って思った。それがおもしろかったから、そのことを詩にする!」
もう家を出る時間だったので、廉太郎はランドセルを勢いよく背負って靴を履き始めた。
「なんか僕書けそう。ありがとう。行ってきます!」
そしてそう言って、家を出ていった。
帰ってきた廉太郎に、「国語の授業で、詩書けた?」と聞いたら「書けた!」と言う。
どういう詩にしたのか尋ねると、廉太郎は朗々と暗唱してくれた。
『ダイヤモンド』
ダイヤモンドって心みたいだね
とお母さんが言った
そのときぼくは、詩を書こうと思った
はじまりはダイヤだった
僕はダイヤに、ありがとう、と思った
言い終えて、廉太郎は恥ずかしそうに笑う。
それと同時にわたしは「すごいね!?」と心から言った。
思っていたのと全然違って、斬新でとてもいい。
廉太郎が「そうかな? クラスのみんなの詩はこんな感じちゃうかったけど」と言う。
「いや、ものすごく良い詩だ。今からどこが良いのかみっつ言うからちゃんと聞いて」
いつになく興奮しているわたしに、廉太郎は目を丸くしていた。
「まずひとつめ。この詩には嘘がない。わたしが言った言葉を、廉太郎はそのまま書いてる。自分が考えたように書いてないよね」
「うん、僕が言ったんじゃないからな」
「嘘がないのはすごく大事なことや。それだけで強い詩になる」
詩なんてほとんど勉強したことないけれど、そう思ったのでそう言った。廉太郎は嬉しそうな顔で聞いている。
「ふたつめ。なぜダイヤと心が似ているのか、この詩には答えが書かれていない」
「そう。先生に、『ダイヤのどこが心みたいだって、お母さんは言ったんですか?』って聞かれてん」
「それでいい。答えは書かなくていい。読んでいる人が考えて、その人なりの答えを持てばいいんだから」
「そうなの?」
「うん。そうしたら、忘れないでしょう? 自分で出した答えを、人はなかなか忘れないよ。そしてこの詩のことも忘れない」
「ふーん、そうかもな……」
廉太郎はうなずいている。
「みっつ目。『はじまりはダイヤだった』の部分がめちゃくちゃいい。これは、廉太郎の心の中にある『原石』を表してる」
「え、どういうこと?」
「廉太郎の中に『詩を書きたい』という気持ちが芽生えたということは、廉太郎の心の一部が輝き始めた瞬間でもある。『ダイヤモンド』という言葉が、廉太郎の中の『ダイヤモンド』を導き出したということだよ」
「あんまりそれは、よくわからへん……」
持論をまくしたてる母親に、廉太郎は困ったような顔をしていたが、とても嬉しそうだった。
「とにかくすごくいい詩だってこと。こんなの書けるなんて、びっくりした!」
わたしも彼の作品が生まれる瞬間に立ち会えて、とても嬉しかった。
この日、わたしは「書く」ことの一部を廉太郎に引き継いだ気がした。
技術のようなものは何も伝えられていないし、その詩が先生やクラスメイトにどう評価されたのかはわからない。
だけど、「書きたい」と「書けそう」を感じる瞬間、そして「書けた」瞬間までを、彼に経験してもらうことができた。
その一巡がどれだけ難しいことなのかを、わたしは知っている。だから、廉太郎が一巡できたこと自体が、とても嬉しいことだった。
この一巡、このひとつの小さな円が、彼の財産になったらいいなと思う。
わたしが教えられることなんて数少ないけれど、また一巡できるように、常に「書けるよ」「できるよ」と励ます存在でありたい。
わたしがいなくなっても、彼の中にその小さな円が、いつまでも残ってくれたらいい。
心のどこかにその円さえ残っていれば、彼はまたいつでもその外側を一巡できると思うから。