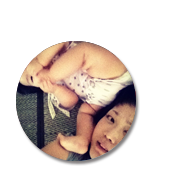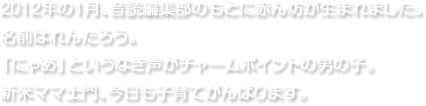子供たちの心って舟みたいなもの2020.3.1

最近、廉太郎が友達とあまりうまくいっていなかった。
仲が悪いわけではないのだけど、遊んでいて嫌な思いになってしまうことがたびたびあったそうだ。
詳細は省くけれど、先日ちょっとしたことがあって、それが表面に出た。
彼はそれまでずっとわたしの前で泣いたり弱音を吐くことを我慢していたらしくて、
「こんなことを言っていいのかわからんのやけど」
と前置きしてから、これまでにあったことを泣きながら話してくれた。
もう学校に行きたくないと思うときもある、と。
わたしはその事実にももちろんショックを受けたけれど、そのことに自分が気づかなかったこと、そして気づいていたとしても「大したことないだろう」とたかをくくっていただろうことにとてもショックを受けた。
すぐに学校の先生に電話をして相談した。廉太郎には休みたかったら休んでもいいと話したし、嫌な思いをさせられたら怒ってもいいんだということも話した。なんならわたしがかわりに怒ってやるということも言った。廉太郎はほっとしたのか笑って「ありがとう」と言ってくれたけれど、わたしはなんて無力なんだろうと思った。とにかくすぐにできることは、先生たちに相談することだけだった。
その後、学校の先生がすぐに対応してくれて、子供たちの間で話し合いがおこなわれた。仲直りもちゃんとできたということだった。
廉太郎はそのことに満足していたみたいだったけれど、わたしの気持ちは沈んだままだった。
自分に何ができたんだろう、そしてこれから何ができるんだろう。
もしも今後同じようなことがもっとエスカレートした形で起きたとき、わたしは一体どうしたらいいんだろう。
わたしは自分のことにかまけすぎて、廉太郎をちゃんと見ていられなかったのかもしれない。そんなことをもやもやと考え続けていた。
朔太郎を迎えに保育園に行ったとき、ふと、ある保育士さんにその話をしてみようと思った。
その保育士さんは前々から、朔太郎だけでなく廉太郎の様子も気にかけてくれる人だったから、相談に乗ってくれるかなと思ったのだ。
すると話をする前に、保育士さんに「お母さん、なんかお疲れのようですけど大丈夫ですか? よく眠れていますか?」と聞かれた。
笑ってごまかそうとしたらどっと涙が出てきて止まらない。
保育士さんはあわてて別室にわたしと朔太郎を通して、話を聞いてくれた。
「それは大変でしたね。お子さんが辛い思いをしていると知って、お母さんも辛かったでしょう」
保育士さんはまずそう言って、わたしのことを労ってくれた。
「でもわたしもちゃんと気づいてあげることができなかったから。そして気づいても何もできなかったから」
とわたしは答えた。「自分にはこれから何ができるのかなって、ずっと考えているんです」
そんなことを言うと保育士さんは、
「僕はここで保育をしていて思うんですけど、園のなかで起きた問題って園のなかでしか解決できないんですよね」
と言った。
「たとえば園で友達とけんかをして、子供が落ち込んだとします。でもその落ち込みって家では解決できないんですよ。園で仲直りしてはじめて解決できる。それって学校でも同じだと思うんです。こんなことを言うと、家や親ができることはないって思われてしまうかもしれないんですけど……」
保育士さんは、ティッシュを渡してくれながら話を続ける。
「でも僕は、家ができることって『常に安定していること』だと思っているんです。子供たちの心って舟みたいなものだなって思うんですけど、それに対して社会は波だらけで、思いがけず揺れることっていっぱいある。でも、家庭がちゃんといつも凪のように落ち着いた海であれば、ここに帰ってくれば大丈夫だって、子供たちは安心できるし、また社会に出ていけるんですよ。僕は正直なところ、家庭にできるのはそれだけだと思っているし、そしてそれがいちばん大事なことだと思うんですね」
「常に安定していること」とわたしは繰り返す。保育士さんはうなずく。
「学校で何があっても、家に帰ればそこにはいつもとおんなじ場所がある。そこだけはいつも変わらない。そういう帰れる・逃げられる場所があるって、子供にとってはすごく心強いことですよ。それは大人にとってもそうじゃないですか?」
わたしは少し考えてから、「そうですね」と答えた。「大人にとってもそうですね」
保育士さんは「そうですよね」と笑った。
「でも、それだけでいいんですか?」
しつこくわたしが聞くと、「それだけでいいと僕は思います」と保育士さんは言った。
「でも」とわたしはなおも言う。
「でも、それがいちばん難しいことかもしれないですね。『常に安定していること』」
「そうですよ」と保育士さんは笑った。
「僕も小学生の子供がいますが、それがいちばん難しい。でも、子供にとって『いつも変わらない安心できる場所』でありたいなって思っています」
朔太郎と手をつないで帰りながら、保育士さんが言ったことを思い返していた。
常に安定していること。いつも変わらない安心できる場所であること。
わたしはもっと、何かできることがあるんじゃないかと思っていた。
もっと問題にたいして一緒になって働きかけたり、関わっていくのが大事なんじゃないかと思っていた。
でもそんなことをしても解決できないのは、自分の過去や現在を振り返ってみたらすぐにわかる。
そうじゃなくて、逃げ場所であること。休める場所であること。
ここに帰ってくればとりあえず大丈夫だと思える場所であること。
わたしにできるのはそれだけなんだなと思ったし、それさえできれば満点だとも思った。
家に帰ると留守番をしていた廉太郎がテレビを観ながら「おかえりー」とわたしと朔太郎に言った。
「ただいまー」とわたしたちは返し、カバンを置いて靴をぬぐ。
「ほら、手洗いうがいするよ」
「今日はご飯何?」
「鍋」
「鍋かー、鍋好きやけど最近多いな」
「それより宿題終わった?」
いつも同じ言葉。いつも同じ流れ。いつも同じ光景。
わたしが守れるのは、多分この光景だけしかないんだなと思った。
それは無力なんかじゃないし、きっとすごく大事なことだ。
「子供たちの心って舟みたいなもの」という、保育士さんの言葉を思い返す。
小さな彼らの心が、ここでだけはせめて、ゆったりと浮かんでいられますように。