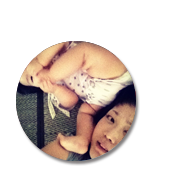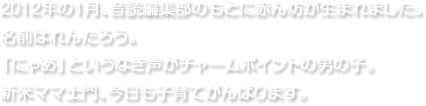冷たい麦茶の入った魔法瓶を持つのが夢だった話2020.8.1

子供の頃、「自分に子供ができたらこういうことをしよう」という夢がたくさんあった。
たとえば「寝る前に絵本の読み聞かせをしよう」とか「一緒にアニメ映画を観て感想を語り合いたい」とか「勉強でわからない部分があったら教えよう」とか。
そのほとんどは自分の両親にしてほしかったことだ。
子供の頃に親にしてほしかったことを、親になった今自分の子供にしているように思う。
夏になると、そういう夢のことを頻繁に思い出すのはなぜなんだろう。
夏休みが途方もなく長くて退屈だったから、夢のことばかり考えていたのかもしれないな。
このあいだ廉太郎に、新しい水筒を買ってあげた。
今使っているものが小さくなったので、もう少し容量の入るものが欲しいと言う。
「みんな、もっと大きい水筒持ってるよ」
廉太郎のその言葉を聞いて、胸の奥がしわっとなった。
わたしはこの「みんな持ってる」という言葉にすごく弱い。
自分自身「みんな持ってる」ものを持っていなかった子供だったので、夢のひとつが、「子供には『みんな持ってる』ものを買い揃えてあげたい」だった。
子供のころそれが叶わなかったのは、うちが貧乏だったからというよりは、同世代間での常識をつかむのが下手な家庭だったからだと思う。
たとえば水筒に限らず、リュックサック、筆箱、タオルハンカチ、家庭科で使うエプロンや三角巾、プールの着替えの際に腰に巻くタオルなど、みんな示し合わせたかのように同じようなキャラクターもの・子供用のものを持っているのに、うちだけ大人用のそれを持たされて、いつもどこかずれていた。
みんなが当日どういうものを持ってくるのか、ああいうものがどこで買えるのか、わたしたち家族には全然わからなくて、わたしは心から「みんな持ってるものがわたしも欲しい」と思っていた。
痛いところをつかれたわたしは、居ても立ってもいられず、子供たちとホームセンターへ向かった。
そして水筒コーナーの前に立ち、廉太郎に「どれにする?」と尋ねた。いろんな種類の水筒の中から、「これかなあ」と廉太郎が手に取る。それは水筒コーナーで一番高価なものだったが、「これと色違いのを、◯◯くんが持ってる」という廉太郎の言葉に、わたしは「それにしよう」と即答した。
いまだに自分は「常識をつかむのが下手」なのではないか、というコンプレックスがある。だから、◯◯くんが誰だか知らないが、他の家庭がこれを持っているのならそれは「常識」範囲内だろうと判断した。レジでお金を払いながら、そんな自分の古傷に気づく。
ホームセンターには、水泳用品やキャンプ用品、虫とり用品などが並んでいる。ああ、こういうのみんな持っていたなぁ、と思う。小学生時代の友達数名の顔が目に浮かんで、
「そっか、わたしもこういうところで買えばよかったんだ」
と、今更わかってもどうしようもないことを、今更わかったりした。
廉太郎の新しい水筒は、魔法瓶なんだけど軽くて、量もたっぷり入って、ワンタッチで吸い口が開けられるし、首からぶら下げることもできる。
新品で空っぽのそれを首にさげた廉太郎が、「買ってくれてありがとう」と言った。
「あとで名前書かないとね」
そう答えながら、彼の笑顔を見て、自分がひとつ夢を叶えたように思って満足だった。
翌朝、その水筒にお茶を入れようとしたのだが、前の晩に麦茶を作るのを忘れていた。
朝作ってしまったので、もちろん麦茶は熱々で、登校時時刻まで冷ます間もない。
しかもよく見れば、魔法瓶の側面に「熱い液体は入れないでください」というシールが貼ってある。このシールは決して剥がすな、とまで書いてあるから、きっと相当な禁止事項なのだろう。スポーツ用の魔法瓶に慣れていないわたしは、「熱いお茶って入れちゃだめなんだ」とその時初めて知った。熱いお茶を入れて氷をあとから入れようと思っていたのだが、ボールで冷ましてから入れるべき?などと逡巡しているあいだに登校時刻がやってくる。
それでしかたなく廉太郎に「ごめん、今日お茶ない」と言うと、「水道水でいいよ。俺、水好きやから」と返ってきた。
仕方なく水道水を入れて持たせたものの、自分ではそれがすごく残念だった。
子供の頃、わたしの家でもお茶が作られていないことが多くて、いつも水道水を入れて行っていたから。生ぬるい水道水は全然おいしくなくて、氷の音をカラコロたてながら冷えた麦茶を飲んでいるクラスメイトがとても羨ましかった。
「自分が親になったら、氷のカラコロ鳴る、冷えた麦茶の入った水筒を持たせよう」
それが、もう一個のわたしの夢だった。
翌朝から晩のうちに麦茶をつくり、一晩冷蔵庫で冷やしたものを氷とともに水筒に入れ、持っていかせるようにした。
廉太郎が首から水筒をぶら下げ、帽子をかぶり、マスクをし、ランドセルを背負う。
ランドセルには、ポケットモンスターの巾着袋。中には同じくポケモンのカップに子供用歯ブラシ、それから小さな無印良品のタオルハンカチが入っている。
廉太郎が玄関でこちらを見て、「行ってきます」と片手をあげる。
わたしはそこに自分の片手をタッチさせ、弟の朔太郎も片手でタッチした。
そのとき廉太郎の水筒からカラコロと氷の音がして、わたしはすごく嬉しくなった。このとき嬉しがっていたのは、子供の頃のわたしかもしれない。
「車に気をつけてね」
そう言いながら、廉太郎を朔太郎と見送る。
「くるまに、きをつけてねー」
朔太郎がわたしの真似をするのを聞いて、
「あ、この言葉、うちのお母さんのだ」
と思った。
母もいつもわたしに「行ってらっしゃい」じゃなく「気をつけてね」と言った。「車に気をつけんさいよ」と。
廉太郎が閉めようとするドアの隙間から、セミの鳴き声が聴こえてくる。
このとき唐突に記憶が蘇った。
それは、ラジオ体操に通っていたある朝のこと。
コンクリートの上で派手にこけてしまい、膝を縫わなければいけないほどのけがを負って流血するわたしを、知らせがあって駆けつけた母がおんぶして連れて帰ってくれた記憶だった。
母は血の量に驚いたのか、涙声で言っていた。
「お願いだから、気をつけて。けがなんかせんといて」
やっぱり夏はいろんなことを思い出すな、と思う。今もわたしの膝には、そのときの縫い跡が残っている。
これも夢だった。これも夢だった。
子供の頃こうしてほしかった。
ずっとそう思っていたけれど、子供の頃のわたしはわたしで、愛されていたのだろうなと思った。
子供の頃に親にしてほしかったことを、親になった今自分の子供にしている。
でも、子供の頃に親にしてもらったこともまた、親になった今自分の子供にしている。
もらったものは受け継いで、足りないものは作り出して。
そうすることで、自分の中の「子供」をわたしは肯定し癒しているんだろう。幼い息子たちとともに、自分の中の「子供」を、自分という「親」を育てているんだろう。
玄関で、兄を見送った朔太郎がわたしを見上げ
「おさらぴかぴかにしたから、ヨーグルトたべる」
と言った。
「えらいね」と答えて、わたしは彼の朝食の皿をさげ、ヨーグルトと子供用のスプーンを用意する。
「子供用のスプーンを持つのも、夢だったな」
そう思いながら、3歳児にいちごヨーグルトを出す。
だけど、大きな大人用スプーンでチチヤスヨーグルトを食べていた自分だって、今のこの子みたいに、おいしそうに頬張っていたんだろう。