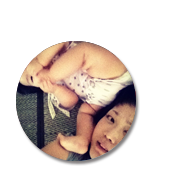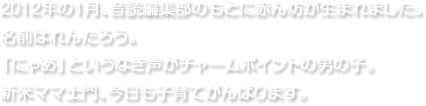埃を眺める、という経験2020.9.10

廉太郎も朔太郎も、習い事をしていない。
朔太郎はまだ3歳だから良いとして、廉太郎は小学3年生なので、なにかしら習わせた方が良いかなと思って、一時期水泳教室に通わせていた。廉太郎も了承はしたものの、わたしがなかば無理に通わせ始めてしまったので、半年くらいで辞めてしまった。大声で叱るコーチが苦手だったらしい。辞めたときには、ものすごく清々しい顔をしていた。よほど嫌だったんだと思う。
「他に何か習いたいことある?」
と聞いたら、「ない」と言う。「ぼくはゆっくりしたい」と。
何を疲れたおじさんみたいなことを、と思ったのだけど、ゆっくりしたいと言う子を動かすのもしのびない。絶対続かないし。
というわけで、廉太郎は土日がガラ空きになり、友達と遊びに行ったり、家で本を読んだり、テレビを観たりして過ごすようになった。英語や空手や水泳や、そろばんやプログラミングやピアノなどと、友達はいろんな習い事をしているなか、廉太郎は実にのんびり過ごしている。
今始めておけば将来ものになるかもしれないのに、とか、教養を身につけるには早いほうが良いだろうに、とか、いろいろ考えたけれども、そういうのは全部自分のコンプレックスなんだろうなと気づいた。
わたしは子供の頃、ほとんど習い事をしていない。
まわりの友達はみんななにかしら習い事をしていたので、遊びに誘っても断られてしまって、すごく退屈だった。あの子は月曜に塾、あの子は木曜にバレエ、あの子は金曜に硬筆、などとみんなの予定は頭に入っているのに、わたしの予定はいつも空っぽ。それが本当につまらなかった。
小四のころ、予定を埋めるためだけに塾に自ら行こうとしたが、入会金と月謝の高さに驚いてやめた。親は行ってもいいよと言っていたけど明らかに無理をしていたので、「塾なんか行かなくても満点とってみせる」とわたしも無理して返事した。
友達は「いいなあ、塾行かずにすんで」と言っていたけど、わたしは塾に通う友達のほうが「いいなあ」だった。なかなかうまくいかないものだ。
小六で月謝が安い公文を見つけて通い始めるまで、その退屈な日々は続いた。
退屈だったわたしは、ずっとテレビを観たり本を読んだりしていた。
それにも飽きると本当にやることがないので、宙に浮かぶ埃をただ眺める。埃って汚いもののはずなのに、西日に照らされると粉雪みたいに綺麗に見えた。埃って何からできているんだろう。本当に汚いものなんだろうか。手を伸ばして取ろうとしても絶対に取れないのはなぜなんだろう。そんなことをとりとめもなく考えていたのを、いまだに覚えている。
だから廉太郎が、習い事もせず「ゆっくりしたい」と言い出したとき、思い出したのが西日に照らされるキラキラした埃のことだった。別にゆっくりと優雅に過ごしていたわけではないが、なんだかひどく懐かしくなり「まあ、埃を眺める時間も必要かもね」とわたしは言った。
「なにそれ?」
「お母さんは子供の頃、あまりに退屈すぎて、ずっと宙に浮かぶ埃を眺めとったんよ」
「えー、それおもしろいの?」
「おもしろいわけないじゃん。でも、ああいう時間が子供には必要なのかもしれん」
「なんで? 埃を見ることが?」
「うん。なんていうか、空白の時間? なににも埋められていない、空っぽの時間っていうか。大人になったら、いやでもぱんぱんに埋められるんやし」
そう言いながら、ものは言いようだよなと思う。
あの頃のわたしは、いつまでも続くような空っぽの時間を持て余し、何かの用事で埋めてほしくてたまらなかった。目の前の埃にすら感動するほどに、わたしは退屈しきっていた。
埃を眺めながら、子供って無力だなと思った。自分でどこかへ出かけることも、何かを買うこともできない。まるで自分が小さな虫にでもなったかのようなあんな時間は、あれ以来ない。
いろんな経験をすることが大事だとよく言われるけれど、何も経験しないで心底退屈している、というのもひとつの経験のような気がする。
「ああいう時間を過ごすっていうのも大事だよ」
わたしはわたしの過去を肯定するためにそう言った。
「子供は本来ひまであるべきなんだよ」と。
だからゆっくりしていいよ、と言ったら、廉太郎は喜んでいた。
彼が欲しがっている時間と、かつてわたしが過ごした時間はおそらくちがうものだけど、わたしはわたしの幼い頃のあの時間を肯定したかったんだと思う。なんの役にも立たないものを美しいと思えたあの時間は、やっぱりわたしにとっては必要な時間だった。
そんなおり、廉太郎が仲の良い友達から誘われて、スポーツ少年団のバレーボールクラブに入ることになった。土日の午前中は練習に向かうのだという。
バタバタと準備をしている廉太郎を見ながら、「ほら、やっぱりすぐに埋められるもんなんだ」と思った。子供がひまでいられるのは、ほんの一瞬なんだよ。
廉太郎は、光る埃を見ただろうか。
ちょっとさみしいと思ったのは、多分幼い頃のわたしだろう。