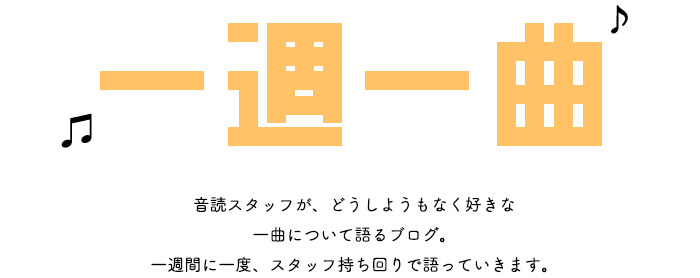第41週 ヨンヨンスン / イ・ラン2017.5.19
このあいだの金曜の深夜に、メトロに行ってきました。
先週末に終了した、国際写真祭・KYOTO GRAPHIEのナイトイベントへ。
90年代に開催されていた、「エイズ・セックス・セクシュアリティ」がテーマのパーティ『CLUB LUV+』の復活。
そこに、韓国のミュージシャンのイ・ランが出演するとのことを知りました。
わたしはイ・ランの大ファンです。
以前も、この『一週一曲』でイ・ランの曲について書いています。
これまでに彼女が出したアルバム『神様ごっこ』も『ヨンヨンスン』も、両方大好きで、一度でいいからライブを観てみたいと常々思っていたので、近所のメトロにイ・ランが来るということを知ってとても喜び、子供を寝かしつけて、雨の中自転車に乗ってメトロまで向かいました。
初めて生で見るイ・ランはドラァグクイーンの格好をしていて、髪の毛はきれいな銀色。
すごくよく似合っていて、きれいな人だなあと思いました。
隣には、コーラスのヘミ、チェロのヘジ。
ときどき彼女は、スマートフォンを取り出してWiFiをチェックします。
ライブ会場であるメトロのWiFiにうまく繋がらないらしく、「かわいそうな韓国のファンたち」にライブを配信できないと、さして残念でもなさそうに話していました。
彼女は、韓国の大衆音楽賞をとったときに、そのトロフィーをオークションにかけたことでニュースになりました。
かくいう私も、それで彼女を知ったくちです。
イ・ランはすばらしい作品を生み出しているのに、どういうわけか賞をとった前月の収入が3万円。
お金がなくて困っていたので、賞金も出ない賞のトロフィーを、その場で「一ヶ月分の家賃、5万円から」スタートしてオークションにかけたのだとMCでも言っていました。
そのニュースを観た、韓国のある美容院の社長さんが、
「このかわいそうな女の子の髪の毛は、一生わたしが無料で面倒を見る」
と言ってくれたのだそうで、美しい銀色の髪の毛はその人によるものなのだと、イ・ランは髪の毛を光らせながら言いました。
とても似合っている、と、また私は思いました。
今から『平凡な人』という曲をやる、と、イ・ランは言いました。
「みなさんは、平凡なひとです」
イ・ランは会場のお客さんについてそう言いました。
彼女の声は涼しくて美しくて、ハングルの色が残った発音の日本語もかわいらしくて、彼女の発せられる言葉はすべてすんなり気持ちよく入ってきます、不思議と。
「そして私は、平凡ではないひとです」
会場から笑い声、でも、歌が始まるとみんな静かに聴き入ります。
平凡な私は、非凡なイ・ランの歌声を聴いて、そして、平凡に感動しました。
非凡なイ・ランは、次に『日記』という曲を演るのだと言いました。
「平凡な人は、日記を書きます。私は平凡なので、日記を書きます。
日記を読み返していると、自分が平凡ではない気がしてくる。だから、平凡なみなさん、日記を書きましょう」
彼女は31歳で、私と同い年。
韓国の同世代は「艱難の世代」と呼ばれている、と、彼女は言いました。
不景気、貧富の差、厳しい受験戦争と学歴社会、戦争、政治腐敗。
韓国の若者の自殺率は世界でもトップレベルで、「ヘル朝鮮」とイ・ランは自分の街のことを呼びました。おそらく親しみを込めて。
死にたいな、と思うことがデフォルトの街で彼女は歌っています。
「私は、私のことを歌っています」
と、イ・ランは言いました。
私は社会のことを歌っているのではない、と。
彼女は個人のことを歌っている、でもその個人は、当然社会に属しているがゆえに、結果的に歌から社会が滲み出ているだけなのだと。
だから、日本人にも響くんだなと思いました。彼女はいつだって、ひとりの「私」のことを歌っているから。
だから、海を超えて、ここ(イ・ランは日本のことも異常な国だと言いました)に住む私にも響くのでしょう。
「私の名前はヨンヨンスン
ウィスコンシンで働いています
そこの製材所で働いています
町を歩いて出会う人々
彼らに名前を聞かれたらこう答えます
私の名前はヨンヨンスン
ウィスコンシンで働いています
そこの製材所で働いています」
私も、簡単な日記をつけています。
日記を読み返してみると「自分はこんなことを考えていたのか」と感心することがあります。
少なくとも、この何月何日という一日を私は過ごし、感じたり考えたりしていたのだな、と。
この日の私は、きちんと存在していたのだな、と。
イ・ランの歌はそういう感じがします。
人生は映画的だということを思い出させてくれるというんでしょうか。
私は『キャロル』という映画がとても好きなのですが、その中で、花を買うキャロルを、主人公が隠れて写真に撮るシーンがあります。他愛ない、でもなぜかすごく泣きたくなるシーンです。
彼女の歌を聴くと、そのシーンを思い出します。
映画的というのは、ドラマチックということではなくて、カメラがあれば映画になるのだ、ということです。
(文・土門蘭)