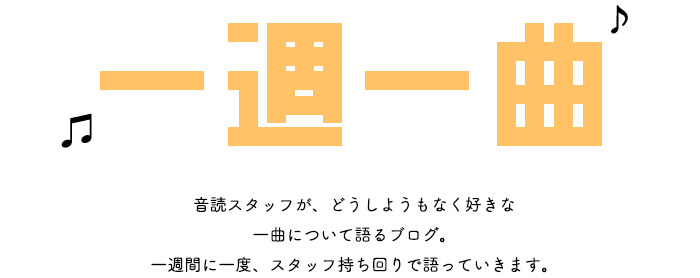第49週 おとなの掟 / Doughnuts Hole2017.7.14
あまりテレビを観ない。
一人っ子で鍵っ子だったので、小さい頃はものすごくテレビを観ていたけれど、本を読んだり音楽を聴くようになってから、徐々に観なくても平気になってきた。
中学以降、友達と芸能人やドラマの話ができなくて、その仲間に入れなかった。
それで、ティーンエイジャーというのは話題の大半をテレビが占めているのだな、ということに気づいた。
テレビの話ができないわたしは、必然的に、自分やまわりの人たちのことについて、話すことが多くなる。
それをあのころのわたしは健全なことだと思っていて、なかば挑戦しているようなところがあった。
テレビの話をさっぴいたら、この場に何の話が残るんだろうと。
さて『カルテット』の話。
保育園のママ友達におすすめされて、録画しているのがあるからうちで観ないか、とさそわれた。
『カルテット』については、誰かがこのように書いていた。
「物語のほとんどが、四人のあいだで、それも密室で、描かれる会話劇」
おもしろそうだな、と思っていたので、わたしは友達についていった。
そして、すべて観た。
最終回のときには、「これでもう、観られなくなるのか」としんみりした。
おもしろい、というだけではすまないような気のするドラマだった。
『カルテット』について語るとき、わたしはテレビの話をするのではなく、自分の話をしていると感じる。
Doughnuts Holeというのがこのカルテットの名前なのだけれど、この四人には決定的な穴がある。それは欠陥とも、欠点とも、しょうもなさとも、言える。嘘つきだったり、臆病だったり、幼稚だったり、単純に仕事ができなかったり。そこを埋めるためにだろうか、それともその穴から出るのだろうか、よくわからないけれど、彼らは音楽を奏でる。
でも、その音楽だって、売れたり認められたり褒められたりすることはほぼない。せいぜい知り合いや子供が手を叩いたり踊ってくれたりするくらい、ごはんを食べながら聴いてくれるくらいで、ほとんどの人は席を立っていく。
「世の中に優れた音楽が生まれる過程でできた余計なもの。みなさんの音楽は、煙突から出た煙のようなものです。価値もない。意味もない。必要ない。記憶にも残らない。私は不思議に思いました。この人たち煙のくせに何のためにやってるんだろう。早く辞めてしまえばいいのに」
こんな手紙をDoughnuts Holeはもらう。そして、そのまま、演奏を続ける。
わたしはそのシーンを、美しいと思った。演奏がよかったからではない。価値もない、意味もない、必要もない。次々と人が立っていなくなっていくなか、それでも演奏を続ける、その非常にかっこわるい人間の姿を美しいと思った。
どぶねずみみたいに美しくありたい、というブルーハーツの歌詞が頭に浮かんだ。四人は決してどぶねずみみたいじゃないけれど、概念としてはどぶねずみみたいなものだなあと思いながら。
このドラマのエンディング曲は椎名林檎が作っている。
「「どのくらい深くまで人が描かれるか」と「どのくらい品が保たれるか」を見極められたなら、その交叉点に唯一のレシピが在る気がして。今回はそれに従いつつ「どの人生にも通底する業」を」
まさに『カルテット』自体がそういうドラマだった。
人はみんな不完全で穴を持っている。
ドーナッツは穴があって初めてドーナッツたりえるように、わたしたちひとりひとりも穴があることで初めて人間たりえるのかもしれない。
このドラマを観ていると、自分がドーナッツみたいな、結構おいしくて許せる存在なような気がしてきて、だからすごく好きだった。
不完全な部分があるから、余剰分が生まれてきて、その余剰分が誰かの不完全な部分を埋めるのかもしれないな。
だって完全体だったら他人なんていらないものね。
だからいろいろ許してね。
(文・土門蘭)